日時:2010年1月12日(火) P.M.7:00開塾
場所:銀座くのや 四階座敷
Text by kuroinu
陶器に限らず、絵でも字でも、また料理でも同じことでありますが、例えば包丁をもって魚を切る、すると、その切った線ひとつで、料理が生きもし、死にもする。気の利いた人がやると、気の利いた線が包丁の跡に現れ、俗物がやると俗悪な線がのこる。北大路魯山人
まったく、俗物はャですな。
70回目の和塾はその「北大路魯山人」のお稽古。講師にお招きしたのは、魯山人の膝の上で育った黒田草臣先生です。
黒田草臣先生
魯山人は、3才の時に美に目覚めた。黒田先生のお話しは、そんなちょっと驚くべきエピソードで始まりました。
明治16年(1883年)3月23日、北大路魯山人は京都市北区上賀茂の貧しい社家(しゃけ=神社の用を務める家)に生まれた。本名は福田房次郎。父親は房次郎が生まれる前に亡くなっている。貧しい家庭環境のため、房次郎は生まれてまもなく里子に出される。その幼年期は悲惨だった。養家をたびたび換え、各所を転々とした彼はまともな食事にすらありつけないこともあった。
3才の時、房次郎は何人目かの養母に連れられ上賀茂神社の裏手にある太田神社のあたりを散歩した。そこに真っ赤な山ツツジがあった。神宮寺山に咲き乱れるその花を目の当たりにした幼い房次郎に何かが作用した。魯山人は後にこれこそが「美を意識する初めての体験だった」と述べている。
生涯を通じて自然美礼賛を貫き、厳しい美意識をもって総合芸術を完璧に追い求めた巨人・魯山人。その出発点は、幼少の頃に見た、こうした洛北の豊かな自然にあったのだろう、というのが黒田先生のお考えです。

芸術は眼に見えない空気、言いかえれば、世人常に言うすなわち感じである。形に見えざる空気の描写、空気の醸成が感じられて具現者を恍惚たらしむるものが、芸術という呼称を許される。北大路魯山人
魯山人と言えば、星岡茶寮がある。日本一の高級料亭として、関東大震災の翌年・大正14年3月、東京赤坂山王台、日枝神社の森の中に開店した。星岡茶寮は、大正9年頃から魯山人が主催していた「美食倶楽部」の流れをくみ、会員制で営業。魯山人は顧問兼料理長だった。「日本の四季折々の変化に富んだ自然の味を料理に取り入れなくてはならない。今こそ、季節感を大事にし、料理を楽しむための空間としての庭や建物、そして調度品や器、趣向を凝らし、茶道の精神にも似た細やかな気遣いを求めるなど、すべて心から客をもてなす総合芸術としての日本料理を供さなくてはならないのだ。そのためには料理人も仲居も斡旋所を通すのではなく、自分の目で探そう。この『星岡茶寮』は働く者にとってもよい環境でなければならない。素材を大切にした美食への執念を燃やし、人を喜ばせる『美食の殿堂』を調度から接客法に至るまで自分流にしたい・・・」魯山人の夢は大きく膨らんだ。
だから、星岡茶寮には魯山人の哲学が横溢していた。例えば、鮎。魯山人によると、鮎は日本海に注ぐ京都の川のものが最良。和知川(京丹波)の若鮎こそが最善だという。「その小味はたとえようもない。若鮎には気品の高さというものがある。その気品の高さは出盛り七、八寸—–一人前の鮎に比べて問題でないまでに調子の高さがある。口ぜいたくを極めた後に初めてわかる味である」(魯山人味道) そこで、魯山人はこの和知川から東京赤坂の星岡茶寮に鮎を運んだ。それも生きたままで。航空路も高速道路もない時代。列車の中に大量の清水を積み込み、桶に入れた鮎に昼夜を問わず常時その清水を注ぎかけつづけ、山王台の茶寮まで。
いくら日本一の高級料亭でもこの仕入れでは採算度外視も甚だしい。同じ頃、魯山人は北鎌倉に自らの住処と仕事場をつくった。これが総面積7000坪の壮大なもの。中には古陶磁器参考館などもあり、そこに魯山人は一流の美術館をも圧倒する国宝級の逸品含む3500余点の作品を買い入れた。そうした費用は皆、星岡茶寮の売上げから。「星岡は道のために努力をしているのだが、自分でいうのは変だが、こんなのはどこにもありませんよ。初めから利益のために商売してるんじゃ、本当のことは出来ない。勘定を合わすことばかり考えていてはだめだ」(美味放談) で、結局、顧問兼料理長の魯山人は星岡茶寮を追放されることになる。

なにごとも慧眼に触れるところがなければならぬ。おのれの眼を世調に曇らしてはいけない。注意力を鋭く、厳しくして、自然の真を観て行け。観る力がないと知ったら修行をすることだ。どう修行するかは、先ず自ら考えを廻らしてみる事だ。北大路魯山人
魯山人の創作活動の初めは「書」だった。明治28年(1895年)京都で行われた内国勧業博覧会で竹内栖鳳の画に出会った彼は画家を志した。しかしあまりに貧乏だったので画材が買えない。書なら筆一本でなんとかなると書の道を進み出す。すべて独学で。22才の時、房次郎(後の魯山人)は隷書体で書き上げた千字文で日本美術展覧会の書の部に応募。ほとんどが五十才六十才の老齢の書家を抑えて一等賞二席を得る。その作品は時の宮内大臣田中光顕が買い上げている。書家として独り立ちした房次郎はその後朝鮮に渡った。逗留3年。朝鮮と中国の漢字文化を学び、朝鮮各地の陶器を研究する日々だった。
帰国し雅号を大観とした彼は、東京京橋に居を構え、書と篆刻、看板を生業にして生活を始めた。その後、近江長浜の紙問屋河路豊吉の食客となる。ここで大観=魯山人は多くの篆刻・落款・扁額を産み出している。河路家の向かいにあった安藤家では、その別荘で一室の内装をすべて任され、これを「小蘭亭」と名付け、扁額はもとより襖絵や天井画、襖や把手、扉の透かし彫り、戸袋の意匠まで創作している。お稽古でも見た「七本鎗」の扁額もこの頃。魯山人は、河路の紹介でその後地元の銀行の頭取・柴田源七の食客となるのだが、当時の近江にはこうした富裕でありかつ芸術文化への造詣深く、支援も惜しまなかった人物がとても多かったようだ。「損して得取れ」の近江商人たちだったのだろう。
近江につづき山代温泉に逗留した魯山人はそこでも多くの作品を残した。ここで魯山人は後の創作につながる食や器に関する多くを学んだ。山代温泉は魯山人にとって果敢な創作の場であると同時に、総合芸術につながる貴重な体験の場でもあった。
金沢から戻った大観=魯山人、今度は東京で古美術の鑑定家を始める。出来る限り多くの逸品に触れるためにもっとも手っ取り早かったのが鑑定家だった。この頃、福田大観は正式に北大路魯山人を名乗り始める。魯山人の鑑定の評判を聞きつけた人びとが押しかけ、京橋の大雅堂芸術店は盛況に。やがて店に集まる顧客に魯山人は料理を振る舞うようになる。これがかの「美食倶楽部」となり、後の星岡茶寮へとつながる。
星岡茶寮と同時期に開いた北鎌倉の仕事場が星岡窯。魯山人はここで陶磁器の創作を始める。今では、魯山人の代名詞となっている陶芸も、彼の総合芸術のひとつとして、美食倶楽部や料亭星岡茶寮の器づくりを端緒として着手されたのだ。魯山人のつくる陶芸はともかく多様だ。染付、色絵に始まり、青磁、白磁、信楽、伊賀、粉引、刷毛眼、唐津、萩、志野、織部、黄瀬戸、瀬戸黒、金襴手、備前、金銀彩・・・。それらすべてが高いレベルにある。陶芸は魯山人芸術の大きな比重を占めることとなった。しかしその始まりは「折角骨を折って作った料理も、それを盛る器が死んだものでは全くどうにもなりません。料理がいくらよくても容器が変な容器では快感を得ることができん」だから器を自分で創る、ということだったのだ。

由来、最高と称する芸術は、絵であっても書であっても、いとこともなげに無造作に出来ているものである。無法の法を悟っているかであろう。北大路魯山人
お稽古では、魯山人の人生を追いながら、多くの作品を鑑賞しました。書あり、篆刻あり、看板あり、絵画あり。染付の向付、染付ヘンコ花入、織部の鉢、赤呉須徳利、いっかん木の葉銘々皿、日月椀、武蔵野富士図、鉄製の置行灯、かにの絵マル平向、糸巻模様平向付、備前土クシメ花入、良寛詞筆筒、赤志野ビアマグ、銀彩徳利、銀三彩木葉皿・・・。本当に多様です。総合芸術の巨人たる所以。あらゆる作品を高いレベルで着地させる類い希な創造力。織部で人間国宝に内定したのに、それを断ったというのだから、凄い人です。
お稽古の最後に、和塾恒例ですが、黒田先生にお持ちいただいた魯山人の作品を塾生が手にしました。良いものは触ってわかる、てことですね。わかりました? あなたが適当に持ち上げてるそのお皿、売価を知ったら手が震えちゃうんじゃないかと思うが、無知というのは強いものです。

魯山人が亡くなったのは昭和34年(1959年)12月21日。今からちょうど50年前のことです。なんとも形容しがたい濃密な76年の生涯でした。
希有の巨人に(文字通り)触れる贅沢なひとときでしたね。黒田先生、ご同行いただいた黒田耕治さん、ありがとうございました。
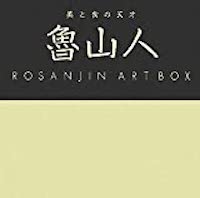
美と食の天才 魯山人 ART BOX
黒田 草臣 / 講談社

器―魯山人おじさんに学んだこと
黒田 草臣 / 晶文社

陶芸家列伝 魯山人おじさんに学んだこと (講談社プラスアルファ文庫)
黒田 草臣 / 講談社
